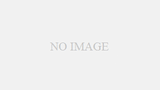こんにちは〜〜「でちん」です!!
本日のSHSは「宅建士試験」の中でも「法令上の制限」について取り上げます!!
法令上の制限というのは主に「都市計画法」と「建築基準法」に関しての内容です。
「宅建業法」「民法」の方が配点が多く、試験勉強上のモチベーションが低いかもしれません。
しかし、土地を検証する為の知識が「法令上の制限」に詰まっているので、「なぜこのような知識を宅建士に求めているか?」と考えていきたいと思います。
今回のSHSを読んで、今勉強している内容が、実際に活用される場面を少しでもイメージできるようになっていただければ嬉しいです!!
法令上の制限
法令上の制限からは毎年「8点」程度の問題が出題されます。
内容は、「都市計画法」と「建築基準法」に関しての知識を問われます。
各法律に関して、実務をやる上で知っておかなければならないポイントについてまとめていきます。
都市計画法
都市計画法でのポイント
「実務」「試験」どちらでも、開発行為に該当するか否かが分かればOKです!
開発行為に該当するかを完璧にして試験に臨むのは中々ハードルが高いので、最低限テキストに載っている事例は覚えてください。
一級建築士でも完璧に何が開発行為に該当するかを把握できません!
だから、「開発コンサルタント」という職業もあるのです!
それよりも、「なぜ開発行為に該当するか否かを判断する能力を問われているのか?」ということに着眼して理解を深めましょう。
なぜ開発行為に該当するか否かを判断必要があるのか
開発行為に該当するか否かで「スケジュール」が大きく変わります。
開発行為が不要な場合と比べると数ヶ月、下手すると数年単位で事業が長くなります。
実務で考えると、竣工時期は遅ければ遅いほど収支上不利です。
他にも、開発の設計料や工事費もかかりますし、人件費もかかります。
残念ながら、不動産業は、「かっこいい建物を建てること」より「いかに儲かる建物を開発すること」の方が優先順位が高いので、発注者(H)は開発が不要な土地を見極めて仕入れます。
開発行為に該当すると、事業期間が延び、収支上不利になるので
発注者(H)は開発不要な土地を見極める能力を身につける必要がある。
建築基準法
建築基準法でのポイント
「実務」「試験」どちらでも、土地に対して「何」を「どれぐらい」建てれるか分かればOKです!
【何】
用途(マンション/ホテル/オフィス等)
【どれぐらい】
容積率の上限、容積消化できるか?
「何」
比較的暗記の側面が強いですが、発注者(H)は開発したい用途が建てることのできる土地を仕入れる必要があるので確実に覚えましょう!
「どれぐらい」
建物の面積が大きければ大きいほど、事業性が良くなるります。
なので、容積率が制限される土地なのか?もしくは緩和される土地なのか?というのを見極めれなければいけません。
また、容積率を消化できるかを、実際にボリュームを作成して検証する必要があります。
その際に、「容積消化を阻害する原因」を把握しておくと、「この土地は消化できそうだな」とボリュームを起こす前になんとなく分かるのようになるので、試験でも出題されることがあります!
容積率の制限・緩和
容積率は、「用途地域」で定められます。その上で、以下の制限や緩和を受けます。
【制限】
1,前面道路幅員による制限
(基準法第52条第2項)
2,地区計画等による関係規定による制限
【緩和】
1,幅員15m以上の道路(特定道路)に通ずる道路に接する土地(基準法第52条第9項)
2,地区計画等による関係規定による緩和
「前面道路の幅員」がなぜ容積率に影響を及ぼすかというと、幅員が大きいほど建物利用者の避難経路として有効と考えられる為、幅員が大きいほど大きな建物を建ててもいいよとなります。
容積消化を阻害する原因
「容積率が500%取れる土地でも、実際に図面を作成したら280%しか容積が消化できなかった」ということが結構起こります。
図面を書くのは時間も金もかかりますので、以下の制限がかかるかどうか確認してから図面を作成するかどうか決めるのをお勧めします!
1.斜線制限(道路・隣地・北側)
2.日影規制
3.高度地区(第1種・第2種・第3種)
4.絶対高さ制限
宅建試験では、各項目がどのようなものか記憶しておく必要があります。
実務でも、いちいち調べてる時間はもったいないので覚えちゃいましょう!
以下にポイントをまとめます!
斜線制限(道路・隣地・北側)
・道路は広い方が良い、狭いと不利!
・敷地より「道路・隣地」が高いと良い、
「道路・隣地」の方が低いと不利!
「天空率」という制度を使うと、消化できることが多いのでそこまで気にしなくて良いです。
日影規制
・「商業」「工業」「工業専用」地域は非該当
・土地の用途地域ではなく、日影が落ちるところの用途地域で該当か非該当かが決まる。
北側の用途地域が何かを気にする必要があります。商業地域の土地だから関係ないとは限らないので気をつけて下さい。
また、検討する際に「真北」が正しいかの確認をしてから図面を作成しましょう。
「真北」が1度ずれると、図面も変わってきます。
「土地購入後、真北測量したら容積消化できなかった」とならないように気をつけて下さい。
高度地区(第1種・第2種・第3種)
・第1種が一番厳しい、次に第2種
・真北に対しての斜線制限がかかる
天空率の緩和は使えないです。
また、真北に対しての斜線の為、真北測量してから図面を作成しましょう。
絶対高さ制限
高さの上限が決まっているので、すぐに何階建てまで作れるかを考えてみましょう。
建蔽率などと合わせて考えると、容積が消化しきれるか否かすぐに出てきます。
まとめ
今回のSHSでは「宅建士試験」の「法令上の制限」の中で、実務でよく使うものをまとめました。
漠然と暗記しても試験は合格できますが、せっかく貴重な時間を割いて勉強するので、「こんな風に活用できそうだな」と実務のことを想像しながら勉強してみてください!
今回もみていただきありがとうございます!!