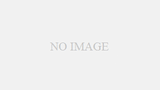こんにちは〜〜「でちん」です!!
本日のSHSは、「VE・CD」の具体例を発信していきます!
そもそもVE・CDとは?という方は過去に配信した以下の記事を参考にしてみてください!
汎用性の高いVE・CD事例5選
今回は、様々なアセットでも使え、設計初期段階に検討すべき事例を5つ紹介します。
設計初期段階のVEは、大きなコスト削減効果が見込めるため、是非参考にしてみてください!
具体的な金額は、各ゼネコンの発注実績などにより変動しますので項目だけ紹介します!
1.階高を下げる
2.RC造・S造でコスト比較する
3.現場打杭と既製杭でコスト比較する
4.断熱範囲・遮音範囲の見直しをする
5.屋上の防水方法を見直す
階高を下げる
1つ目の具体例として「階高」について取り上げます。
基本的にはいい空間をつくるため階高は限界まで高く設定するのが一般的ですが、コストの観点から見るとできるだけ低くすることが重要です。
階高を下げると建物のボリュームが小さくなり、外装・壁の数量が削減されコストが削減されます。
また、建物としての重量が小さくなるので構造計算上有利になり、杭が短くなるなどのコストメリットがあります。
注意点としては、天井高さを確保しながら階高を調整しなければなりません。調整する際は天井内の設備が納まるか、梁が出てこないかを確認しなければならないので、意匠設計・設備設計・構造設計が連携して調整する必要があります。
また、設定した階高を変更することは構造計算をやり直すことにつながりますので、設計初期段階に検討する必要があります。
メリット
・外装・壁の数量が削減される
・建物としての重量が小さくなり構造計算上有利になる
注意点
・天井内で設備が納まらない恐れがある
・梁型などが一部出てくる恐れがある
→意匠設計・設備設計・構造設計が連携して調整する必要がある。
RC造・S造でコスト比較する
2つ目の具体例として「構造形式」の比較を紹介します。
アセット毎に適した構造形式はありますが、選択できる場合は比較することをオススメします。
敷地条件、計画建物のサイズ、アセット毎のRC造とS造どちらが適切か、もしくはS+RCなどその他の構造形式が最適なのかどうかを検証する必要があります。
最近ではコンクリートや型枠の業者がいないことや、36協定による制限で打設する時間が短くなるなどの影響により、RC造の工事期間とコストが上がっています。
S造も物価上昇の影響を受けて工事単価は上がってます。
一方、工事期間は事前に工場で加工したものを現場に持ってきて組み立てていくので、RC造よりも早くなる傾向にあります。
発注者(H)は各構造形式の工事費と工事期間を収支比較検証し、最適な構造形式を決定する必要があります。
現場打杭と既製杭でコスト比較する
3つ目の具体例は「杭」です。
「杭」はコストが高いため、杭の設定が工事費全体に大きな影響を与えます。
杭のコストは「地盤」「杭長」「杭径」「杭の施工方法」によってコストが変動することを覚えておきましょう。
「地盤」はどうすることもできないですし、「杭長」「杭径」は構造設計者が一生懸命設定したものですので大きく変更することはできないです。
一方「杭の施工方法」は、「現場打杭」と「既成杭」で選ぶことができます。
それぞれのメリットとデメリットはありますが、各プロジェクトごとでどちらがコスト的に有利か検証する必要があります。
【現場打杭】
■メリット
・基本的にどの現場でも採用できる
・事前発注が不要
■デメリット
・騒音、振動が大きく近隣トラブルの元となる
・比較した際、現地での作業工程が多い
【既成杭】
■メリット
・騒音、振動が比較的小さい
・工期が短くなる
■デメリット
・工場での製作期間を見越して着工前に事前発注が必要となる
・搬入できない現場がある
注意点としては、「既成杭が搬入できないから現場打に変えたい!」と確認申請下付後にゼネコンが言い出した際、「計画変更が必要な為、着工が遅れる」「コスト増により事業が破綻んする」というリスクがあります。
逆に、「現場打だと近隣と騒音によるトラブルになるの恐れがあるので既成杭に変更したい!」と要望を出した際、「既成杭の製作には数ヶ月かかるので着工が遅れる」「コスト増により事業が破綻んする」リスクがあります。
断熱範囲・遮音範囲の見直しをする
4つ目の具体例は「断熱・遮音」です。
基本的には「外部 – 内部」「専有部 – 共用部」の間の「壁」「床・天井」に「断熱・遮音」性の高い仕様にします。
※発注者(H)、アセットによって考え方は異なる場合がある。
皆さんも実際に平面・断面図で断熱・遮音のラインを蛍光ペンでなぞってみてください。
ここは不要なのでは?というところに断熱や遮音が施されている場合がありますので、一度見直すことをオススメします。
逆に、必要なところにないことが判明することもあります。
なので、設計時には断熱・遮音の考え方を発注者(H)と設計者(S)で協議する必要があります。
屋上の防水方法を見直す
5つ目の具体例は「屋上の防水」です。
屋上の防水方式は何種類かあります。
その中でも「アスファルト防水」とした際の仕上げを
「押さえコンクリート仕上げ」か「露出仕上げ」のどちらにするかによってコストが変わってきます。
【判断基準】
どっちの仕上げにするかは、屋上が一般開放されているか否かで判断すると覚えておきましょう。
一般開放されていれば、防水層を保護しなければいけないので「押さえコンクリート仕上げ」
一般開放されてなく、設備のメンテナンス程度した人が入らない場合は「露出仕上げ」
また、「押さえコンクリート仕上げ」にすると建物の重量が大きくなるのに加え、建物の一番高いところに荷重がかかるため構造的にも不利になります。
つまり、「押さえコンクリート仕上げ」から「露出仕上げ」に変更すると、構造的に有利になるので柱は細く、杭が短くなる等によりコスト圧縮される可能性がありますので、構造設計が本格的に始まる前にどちらの仕上げにするかを決定しましょう。
まとめ
今回は、様々なアセットでも使え、設計初期段階に検討すべき事例を5つ紹介しました。
「なぜ設計初期段階なの?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
理由としては「構造計算」に影響のある内容だからです。
構造計算は時間もかかりますし、コストにも大きな影響を与えます。
また、「構造計算のやり直し」=「確認申請のやり直し」と同意なので設計初期段階に検討すべき事例として取り上げました。
今回取り上げた事例以外にも、設計初期段階に検討すべき事例はたくさんありますので、皆さんも知っている事例があればコメント頂きたいです!
また、冒頭にも書きましたが、設計初期段階のVEは、大きなコスト削減効果が見込めます!
一方、現場に入ると大きなコスト削減効果が見込めるVEを見つけるのは難しくなります。
是非今回の事例を参考に、プロジェクトのコスト調整に役立ててください!
最後までみていただいてありがとうございます!!